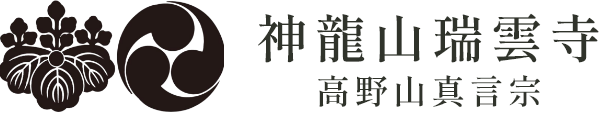葬儀・法要

- 葬 儀
- 法 要
葬儀について
通夜は、亡くなられた方が人として過ごす最後の夜に、ご家族や親しかった友人が集まって故人を偲び行われる行事です。
昔は夜通し行われていましたが、現代では時間を決めて行われるようになりました。
通夜の翌日に行われる葬儀では、真言宗の作法に則り引導作法を行います。
真言宗の僧侶になるためには、得度、受戒、加行、灌頂という過程を踏む必要がありますが、これらの作法を亡くなられた方に御授けし、
戒名という新しい名前と共に仏の世界に旅立つ準備をします。
そして葬儀の後は、亡くなられた方が無事に仏の世界に辿り着けるよう、七逮夜のお参りをさせて頂きます。
瑞雲寺では、お寺にご縁が無かった方からの葬儀のご相談も承っております。
また、葬儀はホールや葬祭場だけでなく、お寺で執り行うことも可能です。寺院での葬儀をご希望の際は事前にご相談下さい。

葬儀までの流れ
flow 1
お寺に連絡
まずはお寺にご連絡ください。日取りのことなどをご相談させて頂きます。
flow 2
葬儀社と日時・場所の決定
葬儀社に連絡をして頂きます。
flow 3
お通夜・お葬式
引導作法をお勤め致します。
- ・瑞雲寺の檀家様以外の方(菩提寺のない方)の葬儀も承っております。
- ・追善法要も行っております。
お問い合わせはこちらから
お電話は下記番号まで
お問い合わせフォームはこちら
法要について
法要は葬儀後に行われる初七日から始まります。
荼毘に付された後、人は中陰の世界を四十九日かけて旅するとされています。
三途の河を渡り、閻魔大王に会うという旅です。
逮夜は、亡くなられた方が無事に仏の世界に辿り着けるよう様々な仏様と共に満中陰(四十九日)まで七日毎に皆でお祈りする法要です。
近年では、初七日は葬儀と同日に行うことが増えていますが、本来は亡くなられてから一週間目が初七日となります。
満中陰の後の法要は、百箇日、施餓鬼初盆供養、一周忌と続いていきます。
瑞雲寺では、納骨は百箇日の法要の際に行っております。ご自宅で法要を行うことが難しい場合は、当寺院で行うことも可能です。
今や家族同然の存在であるペット達の供養も承っております。お墓仕舞い、お仏壇仕舞いなどについても、ご質問等があれば一度ご相談下さい。

代表的な法要一覧
| 法 要 | 時 期 |
|---|---|
| 初七日 | 亡くなられた日から7日目 |
| 四十九日 | 亡くなられた日から49日目 |
| 百か日 | 亡くなられた日から100日目(納骨) |
| 初盆 | 四十九日法要後初めて迎えるお盆 |
| 一周忌 | 亡くなられてから1年目の命日まで(以下同) |
| 三回忌 | 2年目の命日 |
| 七回忌 | 6年目の命日 |
| 十三回忌 | 12年目の命日 |
| 十七回忌 | 16年目の命日 |
| 二十三回忌 | 22年目の命日 |
| 二十五回忌 | 24年目の命日 |
| 二十七回忌 | 26年目の命日 |
| 三十三回忌 | 32年目の命日 |
| 五十回忌 | 49年目の命日 |
お問い合わせはこちらから
お電話は下記番号まで
お問い合わせフォームはこちら